東京大学未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット主催
都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ 第二部 その1
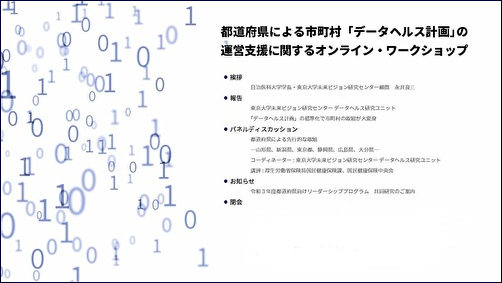
- はじめに 6都県の取組の概要
- テーマ1 都道府県の役割
- テーマ2 「データヘルス計画」を同じ様式に整理して実現したこと (標準化①)
- テーマ3 共通の「評価指標」設定のメリット (標準化②)
- テーマ4 効果的な保健事業のパターン化 (標準化③)
- テーマ5 保健所、国保連合会との共創
- おわりに 1年間の取組を終えて
パネルディスカッション 都道府県による先行的な取組 ―山形県、新潟県、東京都、静岡県、広島県、大分県-
パネリスト; 山形県健康福祉部健康づくり推進課医療保険担当 斉藤和顕 様 新潟県福祉保健部国保・福祉指導課国民健康保険係 武田真紀子 様 東京都福祉保健局保健政策部国民健康保険課医療費適正化担当 春山涼 様、井上奈美 様 静岡県健康福祉部健康局国民健康保険課指導・助成班 福地伸泰 様、土屋厚子 様 広島県健康福祉局国民健康保険課国保医療費適正化担当 仁田千枝 様 大分県福祉保健部 国保医療課保険医療指導班 内田弘子 様
講 評; 厚生労働省保険局国民健康保険課課長 森田博通 様 国民健康保険中央会常務理事 中野透 様
コーディネーター; 東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニット 特任教授 古井祐司
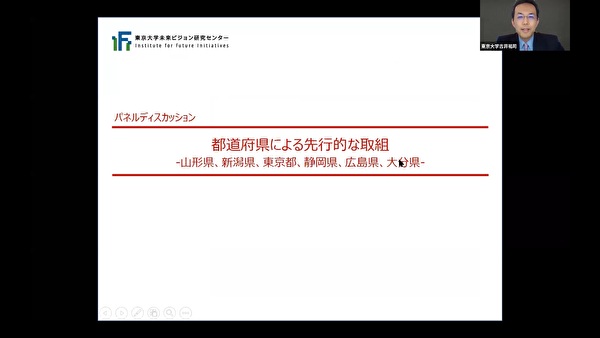

はじめに 6都県の取組の概要
東京大学では6つの都県の皆さんと一緒に取組を進めており、その背景と概要をご紹介します。 まず、静岡県については、2016~2018年度に実施した厚生労働科学研究の一環で、2018年度からモデル県としてご協力をいただき、市町データヘルス計画支援事業を進めています。また、山形県・新潟県・広島県・大分県の4県は、2020年度にスタートした東京大学の「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」を実践されています。なお、東京都に関しては、私たちは地元の大学として3か年かけて都庁の皆さんと共にすべての区市町村への支援を行っていく予定で、2020年度はその一年目でした。
■東京大学「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」における主な3つの取組
自治体の皆さんとの共創のもと研究開発した「都道府県向けリーダーシップ・プログラム」では、下記の3つを主な取組としています。
- 1 「データヘルス計画」の構造化
- 2 市町村支援(分析・評価・助言)
- 3 教育および人材育成
■先行モデル県として静岡県の取組の報告
〈計画の構造化〉 静岡県の市町データヘルス計画支援事業では、2か年かけて全35市町の構造化を進めました。計画を同じ様式に落とし込むことで「データヘルス計画」を俯瞰でき、市町を横並びで比較可能になりました。構造化した素材(「標準化ツール」)は、中間評価・見直しの際の市町支援にも活用しました。
〈評価指標の設定、計画見直しの支援〉 2か年かけて県・保健所・国保連・東京大学で行った全市町へのヒアリングでは、構造化した計画と市町の現状(特定健診・特定保健指導、メタボリック・シンドローム該当者などの状況)を併せて把握することで、それぞれの市町の健康課題に合う組み立てになっているのかについて意見交換しました。具体的には、評価指標の設定や方法・体制、保健事業の組み合わせなどです。ヒアリング終了後は、「フィードバックシート」を作成し、全体計画と個別保健事業の見直しのポイントを整理しました。
〈データ分析と施策への活用〉 県としての施策検討や市町による「データヘルス計画」の運営に活かす目的で、県内全市町のKDBデータ(国保、後期高齢者医療)を使った地域別の医療費・健康状況の特性や地域格差の要因分析を東京大学に依頼しました。分析結果と分析ノウハウについては、市町向け研修会で報告しました。
〈静岡県における共通指標の作成〉 2020年度の「データヘルス計画」の中間評価・見直しに合わせ、県内共通の評価指標を県、国保連、支援・評価委員会、東京大学の4者で連携して作成し、周知しました。この評価指標は現在、多くの市町で活用されています。
テーマ1 都道府県の役割について
はじめに、都道府県の役割についてコメントをいただきます。
東京都: 都の役割は、区市町村を俯瞰して特徴を把握することや、その中で得られた良い事例を横展開することなどだと考えています。 東京都では、全区市町村の「データヘルス計画」の内容を構造化し、ヒアリングや助言を行う事業を東京大学にご協力いただいています。その中で、区市町村の計画や取り組み内容について、それぞれの特徴を把握してきており、今後、必要な支援や横展開につなげていければと考えています。
大分県: やはり「横展開」がキーだと思います。大分県は平成の大合併で、それまでの58市町村から18市町村になり、お互いの状況をつかみやすくなりました。県は市町村で共有したい情報を集約し全市町村へ還元しています。横展開では、まずモデル自治体がいろいろな取組を実施し実践報告をして、次の年に他の自治体で行うというやり方をしています。そうした取組の過程が最終的には市町村自身が自立する支援になり、また市町村間の相互作用につなげることを県としての役割だと感じています。
山形県: 県の役割としては、東京都・大分県と同様、市町村がすでに行っている好事例の横展開が重要だと思います。また、二次医療圏管内の市町村の特色などをよくわかっている保健所を通じて、市町村への支援を強めていきたいと考えています。
広島県: 当県も市町のデータヘルス計画の策定状況を確認し、必要に応じて助言等をしてきました。来年度からは国保連の協力を得て「標準化ツール」を使った研修会を実施し、また情報共有の場を設定するなど、市町の次期計画策定に向けた支援が必要と考え、取組んでいく予定です。
新潟県: 新潟県では来年度からの本格的な事業実施を目指しています。県では保健所を通じた市町村支援を考えています。
- ・まず市町村の状況を捉えること
- ・関係機関と共創して、市町村の自立を支援すること
出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料
テーマ2 「データヘルス計画」を同じ様式に整理して実現したこと(標準化①)
パネリストの皆さんからコメントをいただく前に、ワークショップ参加者から事前に寄せられた主な質問をご紹介します。 「市町村の取組に格差があり、個別の支援が必要と感じています。その際に、様式の雛形のようなものがあると良いのかなど、手探り状態です」、「市町村の職員の人事異動があっても、事業の質を低下させず、継続していくための工夫はありますか」といった関連のご質問がありました。
静岡県: 市町によって保険者の規模はかなり異なりますが、計画を同じ様式に落とし込んで標準化したことで、全体を横並びで比較・俯瞰することができたというのが一番大きな成果でした。 取組が不足している市町には、不足している部分を具体的に指摘してアドバイスができますし、近隣の市町を参考にすることもできます。
東京都: 東京大学の「標準化ツール」によって、計画の構造や健康課題の解決に向けた目的・目標が他の区市町村と比較できる形で整理できました。 「市町村の職員の人事異動があっても事業の質を低下させず、継続していくための工夫は」という質問に対しても、「標準化ツール」が活用可能だと思います。また、事業の見直し等にKDBの活用等が比較的簡単にできるようになればと考えています。
大分県: 大分県では今年度1市がモデル自治体として取組み、その取組と合わせて全市町村で第2次計画の中間評価を行いました。そして、東京大学の協力を得て全市町村対象の研修会を行いました。 この研修会の事前に各市町村は計画を「標準化ツール」に落とし込み、研修当日は質疑応答を行いました。研修会終了後に市町村から、「今までは実施数などのアウトプットの部分が多かったが、アウトカムの達成を考えるようになった」、「標準化により具体的に何をしなければいけないのか明らかになった」、「標準化ツールによって担当が変わっても引き継げる。次年度事業の見直しや関係者以外の人にも示せる」、「国保と保健衛生、介護保険等の庁内他部局と共有しやすい」、「保健師と事務職で情報共有し一緒に考えるきっかけになる」等の意見がありました。市町村、東京大学と一緒に取組んで本当によかったと感じています。
山形県: 山形県では今年度、保健所が主催する市町村を対象とした会議で、「標準化ツール」を使って支援をしています。「標準化ツール」で各市町村の保健事業を「見える化」したところ、市町村ごとに事業の中身の濃淡というか、きちっと標準化ツールに埋められる項目・埋められない項目があることが見えてきました。見える化を通じて、市町村で行われている工夫も見えてきました。 保健所の職員(県側)は、市町村に対して評価の支援やアドバイスをするのですが、これまではどこからアドバイスやコミュニケーションを始めていいかわからないということもありました。このツールを使うことで市町村とのコミュニケーションのきっかけになったのではないかと考えています。 また、今後はツールを使って全市町村の状況を同じ様式で比較すれば、より分析がしやすくなると考えています。
- ・市町村の様子を俯瞰できた
- ・「データヘルス計画」の過不足、保健事業の工夫も見えた
出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料
テーマ3 共通の「評価指標」設定のメリット(標準化②)
「データヘルス計画」の標準化の重要な要素のひとつとなる、共通の「評価指標」を設定することで市町村間を比較できることは、事業を運営する上でのメリットだと思います。テーマ3では、「評価指標」を共通化することについて意見交換します。
静岡県: 静岡県では、市町が中間評価、見直しの際の整理表を作成するときに、ステップ1の部分や、アウトプット・アウトカムをどのように設定すればいいか分からないという意見が多かったため、例として県から共通の評価指標を提示しました。共通の指標を使うと市町で実績を比較できます。その結果、実績の良い市町を紹介したり、保健事業の方法・体制の工夫を抽出しやすくなりました。 また、静岡県ではKDBや茶っとシステムという県独自のシステムがあるものの、これまでは議会の説明の資料などにしか使われておらず、事業評価等のルーティーンには組み込まれていませんでしたが、これからは活用されていくと考えています。
大分県: 大分県では国保連のサポートを受けてKDBシステムの活用がかなり進んでおり、市町村の比較が当たり前の文化になってきました。例えば、大分県の重要課題である糖尿病性腎症重症化予防の指標として、「新規の透析導入」を共通の指標で捉えています。どういった指標ならお互いに共有・比較することで事業の質の向上や方法・体制の工夫に活用できるかを考えており、共通の評価指標は非常に重要と感じています。
広島県: 広島県では今年度の取組を契機に市町の現行計画の評価指標等をみたところ、同様の保健事業でも市町ごとにアウトカム指標等が異なっており、実績を比較するのが難しいことがわかりました。 今後は国保連と連携し、他県の取組を参考にしながら、市町の計画策定状況がよく分かるように一覧表に取りまとめ、まずは糖尿病性腎症重症化予防事業の評価指標の共通化に市町と取り組もうと検討しているところです。
- ・独自+共通の評価指標の設定は有意義
⇒ポイントは、KDB で定常的に集計される指標とすること - ・実績の比較、ノウハウの抽出・共有につながる
出典;「都道府県による市町村「データヘルス計画」の運営支援に関するオンライン・ワークショップ」資料
※ホームページの記事、写真などのコンテンツの著作権は、国立大学法人東京大学 未来ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット、制作者ならびに情報提供者に帰属します。

